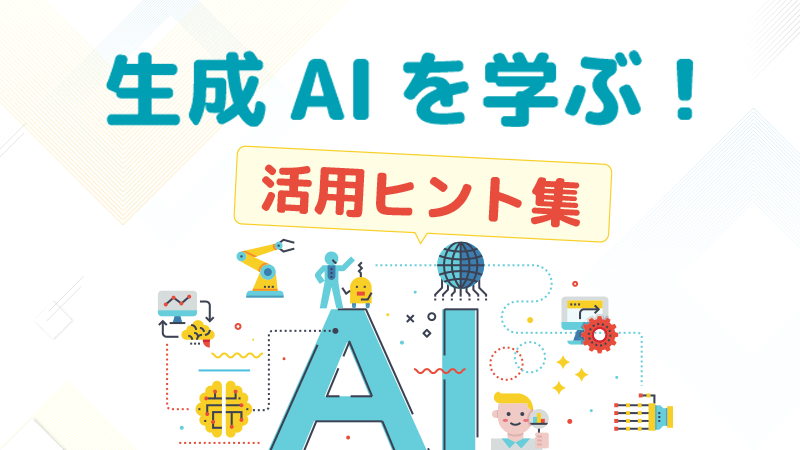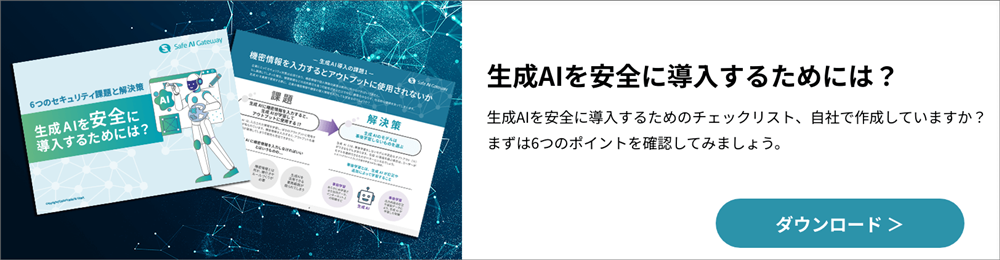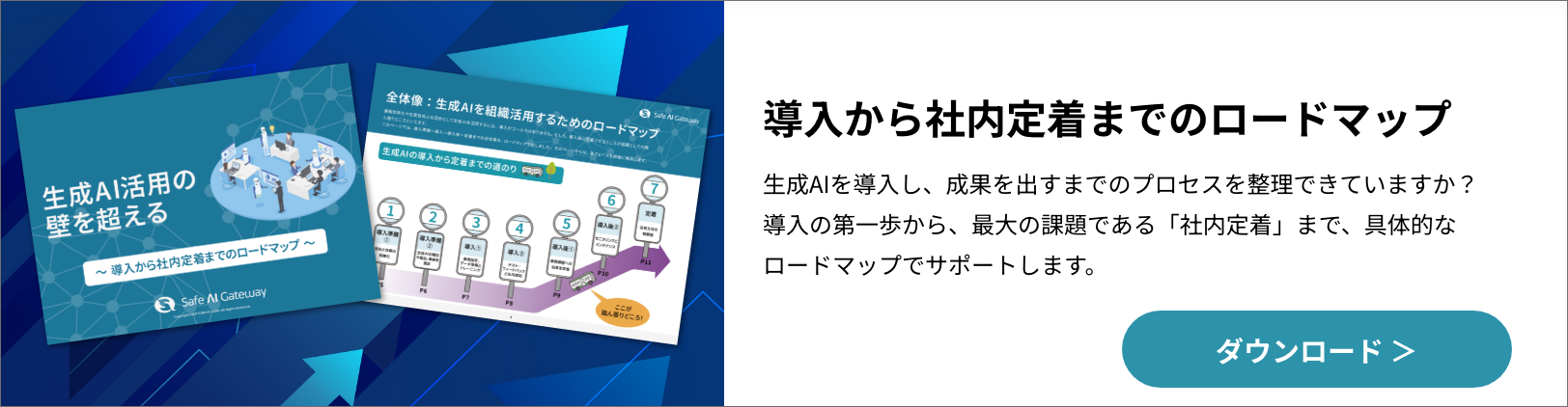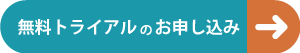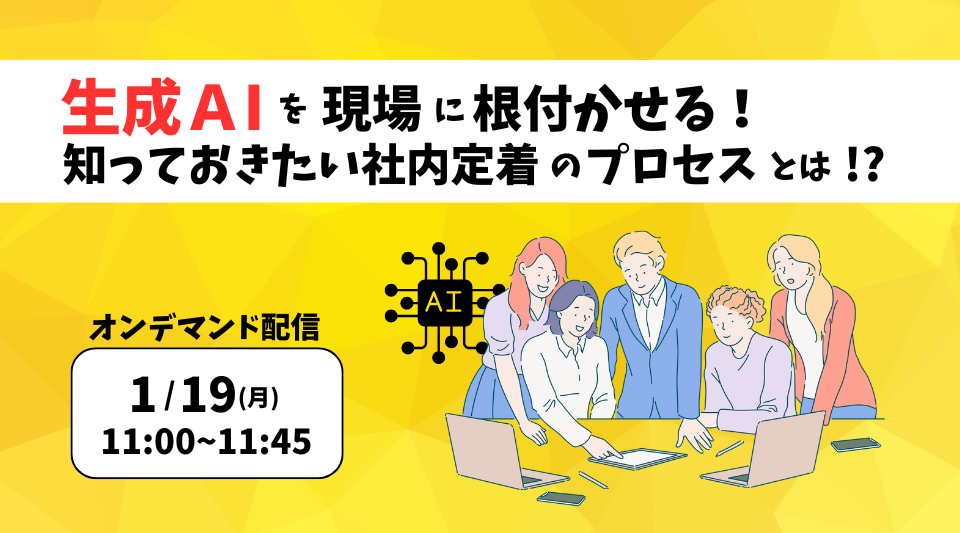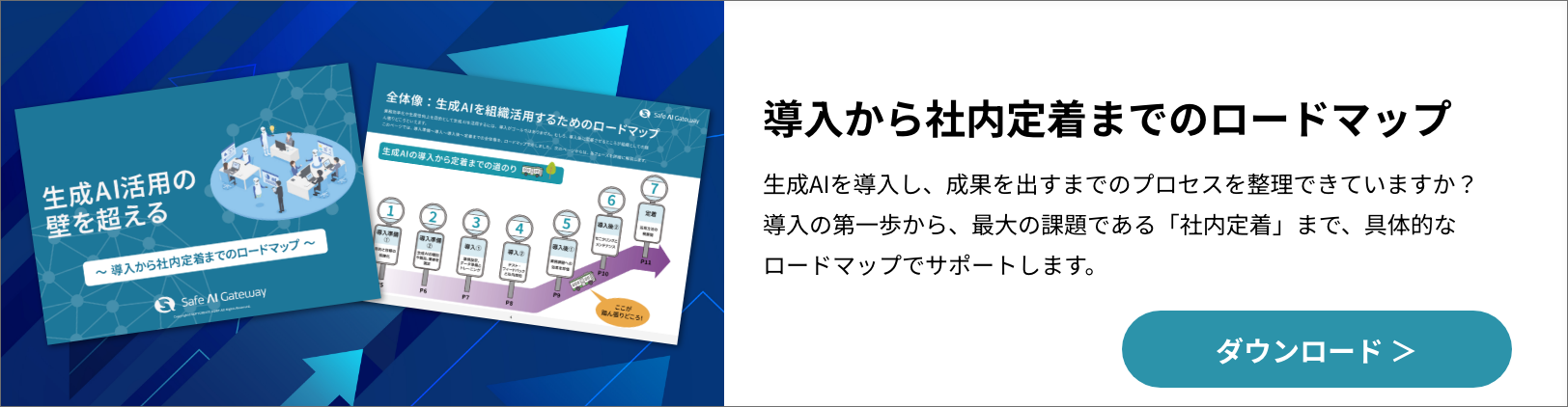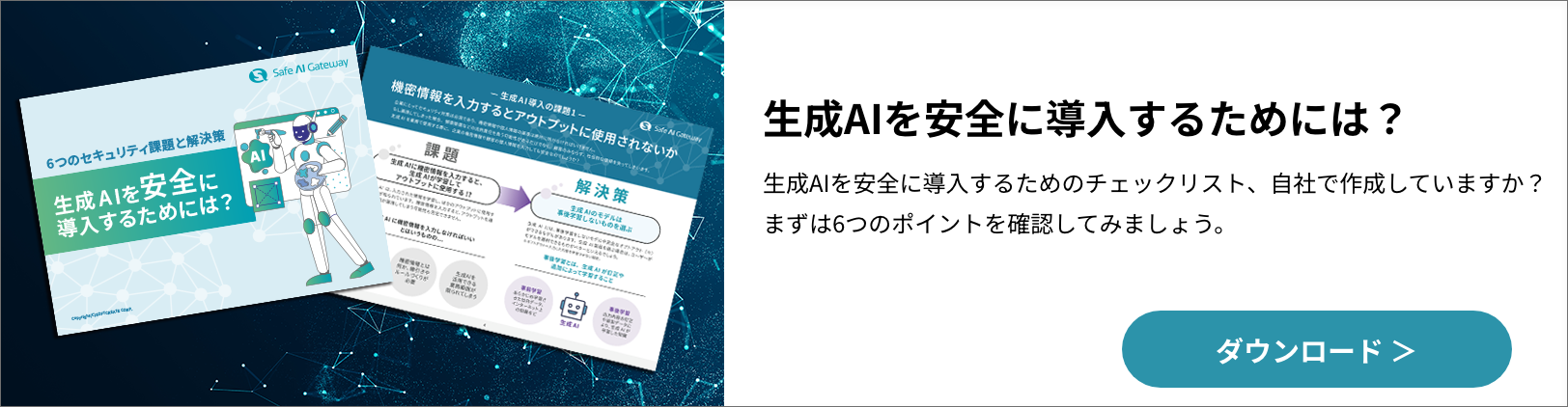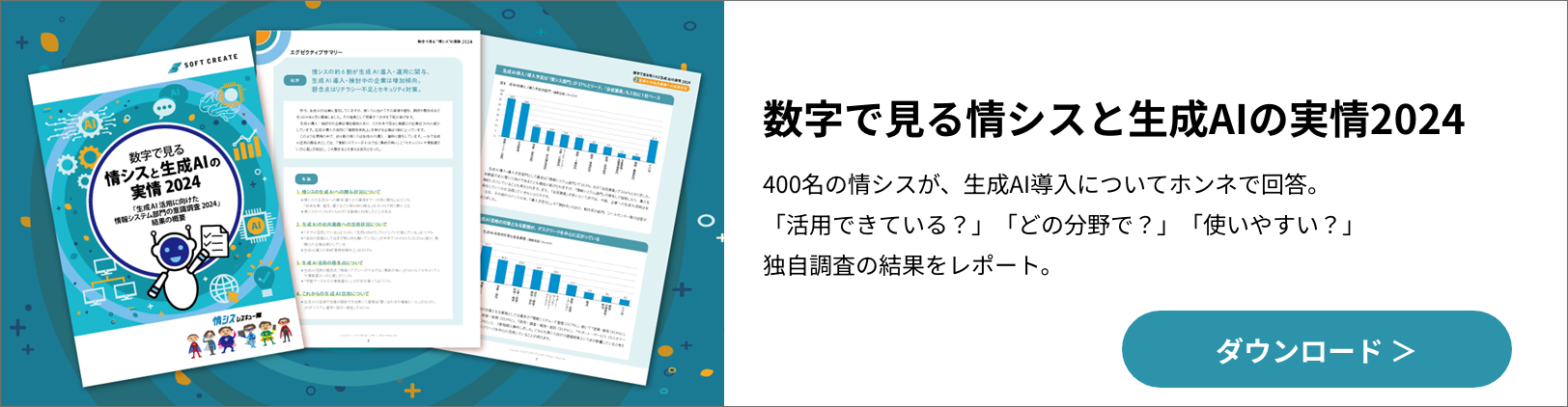生成AIの業務活用が広がる中、組織として導入する際には課題が発生することも多いでしょう。中でもよく見られるのは、活用促進とセキュリティに関する課題です。
この記事では、生成AIを導入して定着させるまでに組織全体で取り組むべき2つの課題と、その解決策について紹介します。
生成AI導入の課題は活用促進とセキュリティ
生成AIを業務に導入する際に課題となりやすいのが、「生成AIの活用促進」と「生成AIのセキュリティ対策」です。
多くの企業が生成AIの潜在的な価値を認識し、導入に取り組んでいるものの、活用促進に苦労しているのが現状です。この背景には、従業員の生成AIに対する理解不足や、既存の業務プロセスとの統合の難しさがあります。
さらに、生成AI導入の課題として、セキュリティに対する不安も挙げられます。個人情報や機密データの保護に対する危機感は年々高まっており、生成AIによるデータ漏洩リスクや、不適切な情報生成に対する懸念は無視できません。
生成AIの活用促進に関する課題と解決策
生成AI導入の課題のひとつである活用促進は、どのようにすれば解決できるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

導入後のPDCAを回す
生成AIの活用促進のためには、導入後のPDCAをきちんと回すことが重要です。まず、生成AIの導入によって期待される効果のKPIを設定し、導入・利用を経て、KPIの達成度を定期的に評価します。このPDCAサイクルを回すことで、継続的な活用効果が表れるでしょう。
例えば、生成AIを活用した文書作成の効率化を目指す場合、作業時間の短縮や品質向上、ユーザー満足度などを定期的にチェックすることで、改善につなげていくことが可能です。定量的な効果だけでなく、定性的な効果も確認することをおすすめします。
導入後も継続調整する
生成AIが業務にフィットしないという問題も、活用を妨げます。この問題を解決するには、導入後も生成AIの継続的な調整が欠かせません。
生成AIツールの稼働状況や従業員の使用状況をモニタリングし、どんな業務にどのように使うかといった、適切に使えるようにするための調整を行いましょう。
同時に、自社データの更新や追加、削除に合わせて生成AIの学習データを定期的にメンテナンスすることも重要です。
また、ボタンを押すだけで定型的なプロンプトを実行できるような仕組みを作ると、プロンプトおよび回答精度の改善が容易となり、生成AIの使用率を高めることができます。
活用方法を横展開する
生成AIの活用が一部のメンバーや部門にとどまってしまうと、組織としての活用が進みません。この問題を解決するには、活用事例を共有し、組織全体で生成AIを活用する体制を整備することが有効です。
先行導入した部門が中心となって、導入から活用に至るまでの成功事例を収集・分析し、他部署へ展開することが活用促進につながります。
また、社内で生成AI活用をリードする人材を育成することも効果的です。この人材が旗振り役となれば、組織全体での活用促進が期待できます。
その上で、成功事例や成果を組織内で共有できる仕組みを作れば、スムーズに社内で横展開できるでしょう。
⇒ホワイトペーパー「 導入から社内定着までのロードマップ 」をダウンロードする
生成AIのセキュリティ対策に関する課題と解決策
生成AIを導入する際のもうひとつの課題は、セキュリティ対策です。ここでは、主要なセキュリティリスクとその対策について紹介します。
機密情報の流出リスク
生成AIは、入力された情報を学習し、ほかの質問に対する出力に利用してしまうことがあります。機密情報についても例外ではなく、深刻な情報漏洩につながる可能性を否定できません。
このリスクに対しては、機密情報を生成AIに入力しないというルールを定めて、厳守することが重要です。企業は利用マニュアルやポリシーを策定し、従業員に周知徹底する必要があります。
また、多くの生成AIサービスでは、オプトアウト設定が可能です。オプトアウト設定とは、ユーザーが入力したデータを生成AIの学習に使用しないようにする機能のこと。この設定により入力データの学習を無効化し、特定の情報がほかの出力に使用されるリスクを低減できます。
ほかにも、セキュリティを担保する外部ツールの利用も効果的です。ベンダー製の生成AIツールには、さまざまなセキュリティ対策が施されたものがあるため、自社の状況に合わせて選ぶといいでしょう。
不正アクセスやなりすましのリスク
生成AIシステムへの不正アクセスやなりすましも、セキュリティ上の大きなリスクといえます。万一、アカウントが乗っ取られると、生成AIへのプロンプトによる指示やチャット履歴を参照され、機密情報が引き出されるかもしれません。
このリスクに対しては、強力な認証機能の実装が有効です。アカウントの安全性を大幅に向上させる効果的な方法としては、多要素認証が推奨されます。
また、企業においては、シングルサインオン(SSO)システムを導入するのも一案です。SSOは1回の認証で複数のサービスやアプリケーションにアクセスできる仕組みで、これを利用すると社内のアクセス管理を一元的に行えます。
さらに、システムログを常時監視し、不審な活動を早期に検知する仕組みを構築することも重要です。
サイバー攻撃やシステム障害のリスク
生成AIサービスの脆弱性を狙ったサイバー攻撃や、システム障害がもたらす影響について想定することも、大切なセキュリティ対策です。これらによる生成AIのデータ改ざんや停止は、企業活動に深刻な影響を与えます。
このリスクに対しては、定期的なセキュリティ診断とシステムのバックアップが効果を発揮します。また、生成AIシステムの動作を常時監視し、異常な動作や出力が発生した際に即座に対応できる体制の整備も必須です。
ベンダー製の生成AIツールを導入する場合は、第三者による継続的な監査を実施しているといったセキュリティ対策を十分に行っているベンダーを選択しましょう。これにより、不正アクセスやサイバー攻撃のリスクの低減が可能です。
⇒ホワイトペーパー「 生成AIを安全に導入するためには? 」をダウンロードする生成AI導入の課題は組織で解決
生成AI導入の大きな課題である活用促進とセキュリティは、いずれも個人での対応は難しく、組織全体で対応することが望ましいといえます。
ここでは、生成AI導入の課題を組織で解決するための、2つの方法について見ていきましょう。

選抜メンバーによる導入プロジェクトを立ち上げる
生成AIを導入する際には、全社横断的に選抜したメンバーによるプロジェクトチームの編成が効果的です。
部署単位で生成AIの導入を進めると、部署間の温度差や取り組み方の違いから、全社的な活用が進まないという課題が生じがちです。部署間のギャップが進めば、生成AIの活用は断片的で一貫性を欠くものとなり、組織全体としての効果や成果も限定的なものになってしまいます。
そこで、IT部門、業務部門、管理部門など、多様な部署から選抜したメンバーでプロジェクトを進めることによって、組織全体の視点から生成AIの活用を検討し、統一された戦略を立てることが可能です。さらに、生成AIの導入を全社的な目標として位置付けるという、アピールにも役立つでしょう。
スモールスタートから全社展開する
最初から全社一律で生成AIを導入しようとすると、コストやリソースの負担が大きくなります。さらに、各部署の業務に合った使い方ができず、導入効果が不透明な状態が続いて社内の反発を招き、導入が失敗に終わるかもしれません。
こうした事態を招かないためには、スモールスタートから段階的に全社展開する方法がおすすめです。最初は特定の業務や部署で試験的に導入し、効果を実証します。
例えば、問い合わせ対応の一部に生成AIを導入して、対応速度や精度の向上を測定し、その結果を社内で共有するといった進め方です。その後、良い結果が得られた時点で、徐々に導入する部署や業務を拡大していきます。
なお、生成AIの導入をスモールスタートする主なメリットは、下記のとおりです。
- <スモールスタートで生成AIの導入を進めるメリット>
-
- リスクの最小化:小規模な導入から始めることで、潜在的な問題を早期に発見し対処できる
- 成功事例の創出:具体的な成果を示すことで、全社展開への理解と支持を得やすくなる
- 段階的な学習:導入プロセスを通じて、組織全体がAIリテラシーを向上させることができる
生成AI導入の課題解決に、生成AIツールの利用を検討しよう
生成AIの導入には、活用促進とセキュリティという大きな課題があります。しかし、しっかりと計画を立て、組織全体で取り組むことで、生成AIの導入から定着までをスムーズに進めることができます。
生成AI導入後の継続的な調整やセキュリティ対策は、ベンダーが提供する生成AIツールを利用すると安心です。導入後も伴走してくれるベンダーの存在は、導入から定着へと至る後押しとなるでしょう。
ソフトクリエイトが提供する
Safe AI Gateway
は、企業が生成AIを安全・簡単に利用できるように開発したサービスです。企業ごとに安全な専用環境を作ることで、セキュアな生成AIの活用を実現します。また、自社データを利用した生成AI型のチャットボットを、自社で簡単に作ることも可能です。
Safe AI Gateway をご検討中の企業様は、無料トライアルで導入前の不安を解消してはいかがでしょうか。2週間の無料トライアルは、下記のリンクからお申し込みください。
Safe AI Gateway をご検討中の企業のご担当者様は、まずは無料トライアルで導入前の不安を解消してはいかがでしょうか。2週間の無料トライアルは、下記のリンクからお申し込みください。