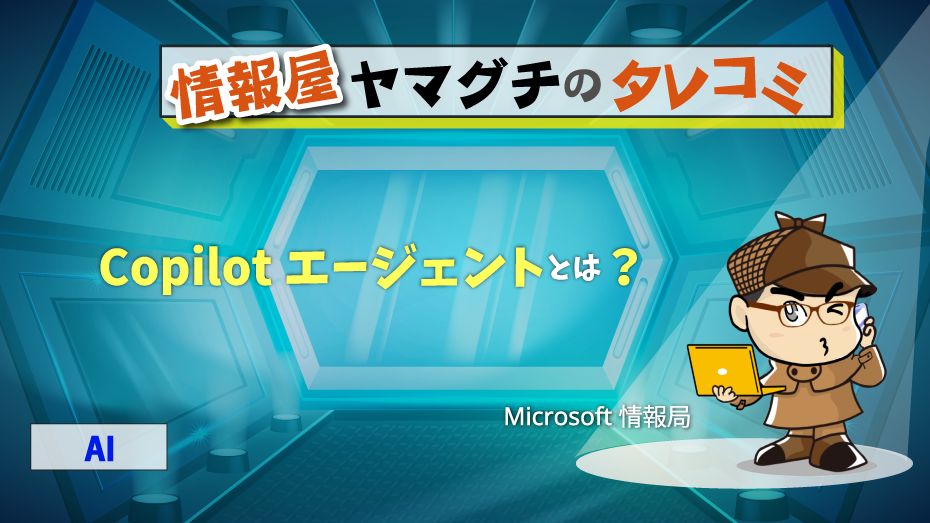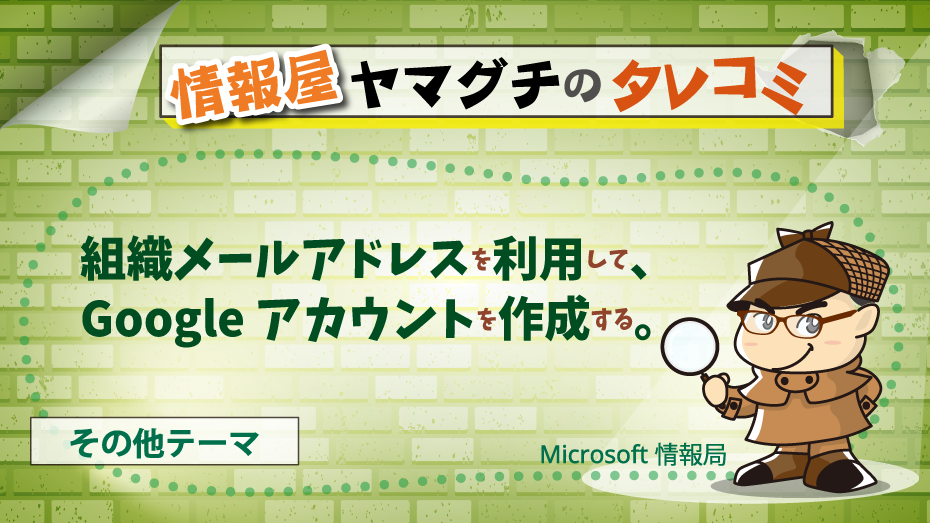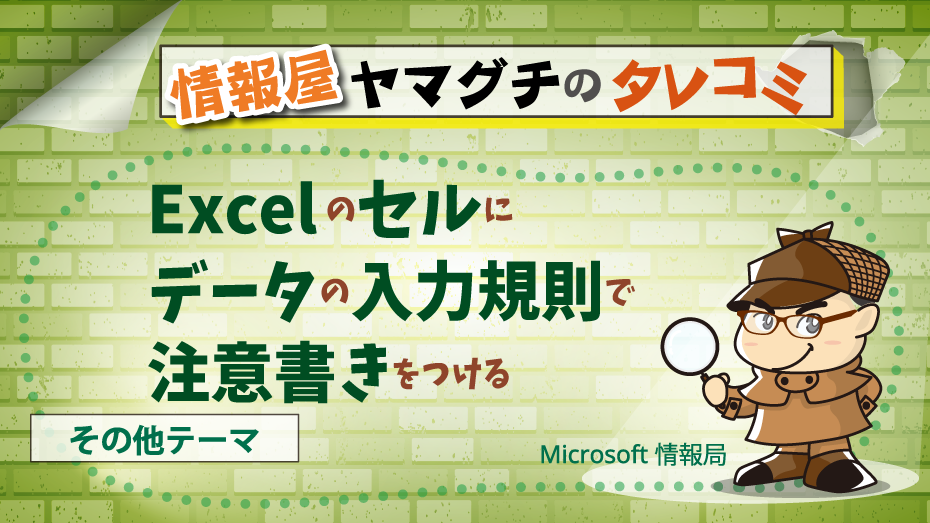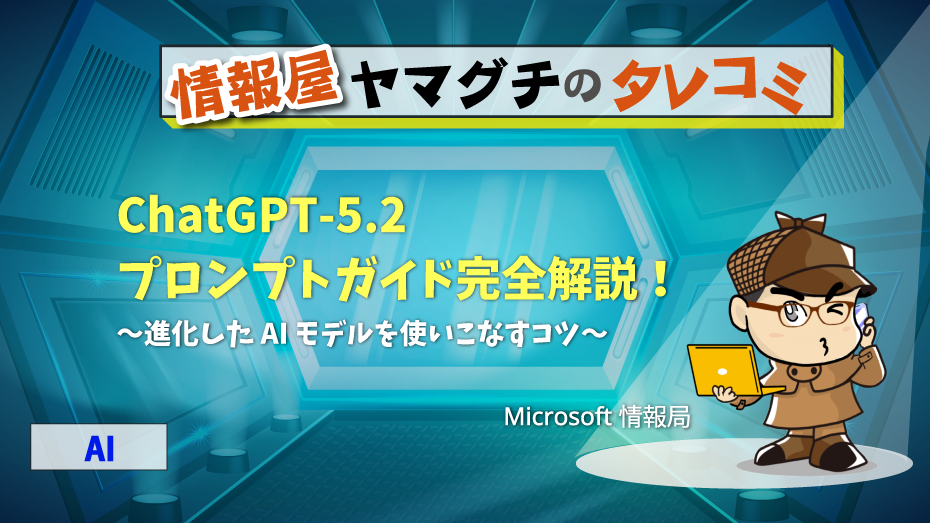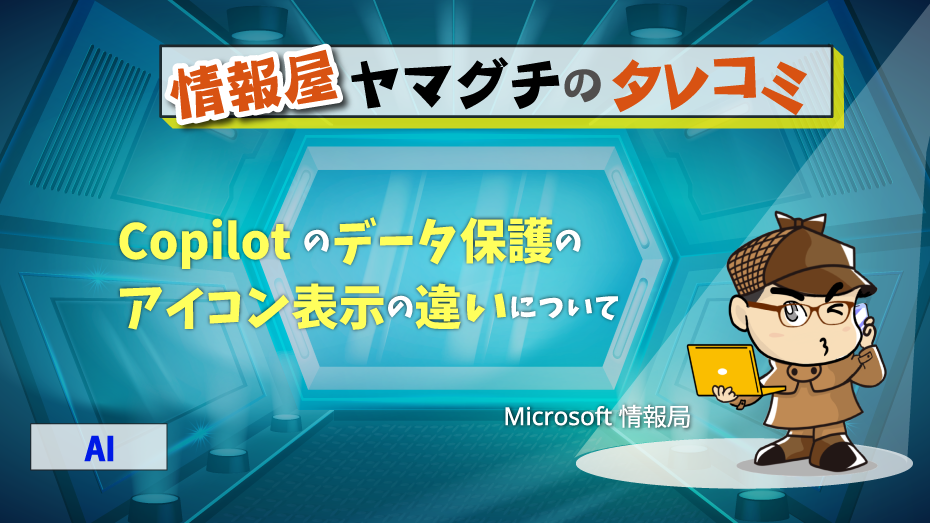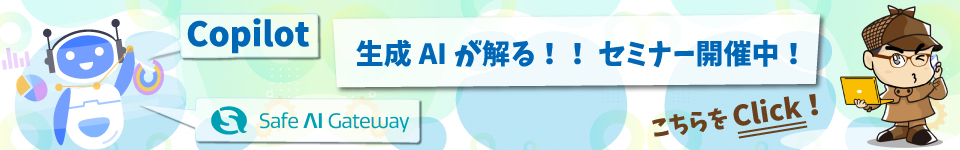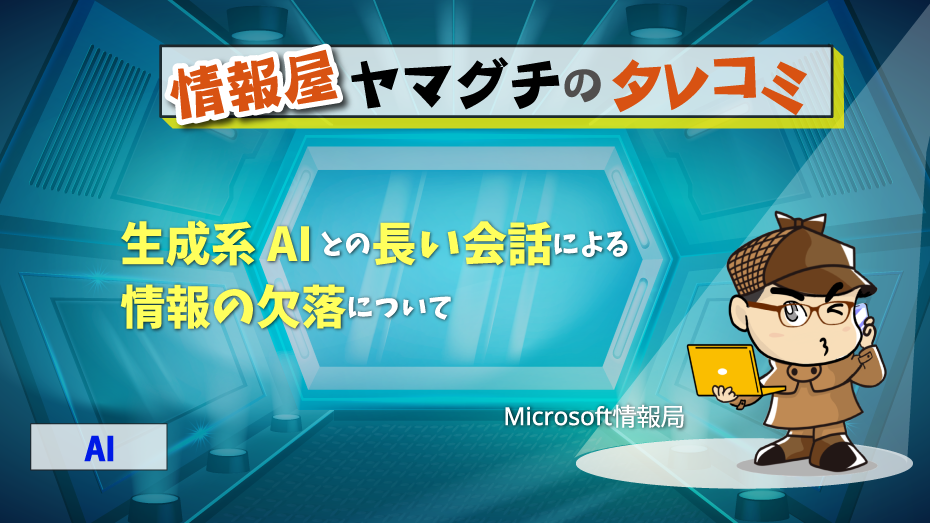
どうも、株式会社ソフトクリエイト で情報屋やってます。山口です。
普段は企業様向けに Microsoft 365 活用のご支援をおこなっています。
生成系AIと1回会話することを、シングルターン、複数回の会話を行うことをマルチターンという呼び方をします(^^
生成系AIとの長い会話による情報の欠落について
このシングルターンと、マルチターンには、それぞれには、以下のような特徴があります。

※ こちらは、生成系AIで今回の記事の内容をイメージした画像を生成させたものです。
◆シングルターン(Single-turn)
特徴としては、1回のやり取りで完結する形式です。つまり、ユーザーが何かを入力すると、それに対してAIがすぐに返答して終わり、というスタイルですね。
たとえば、こんな感じです。
ユーザー:「猫の写真を描いて」
AI:「こちらが猫のイラストです。」
向いている使い方としては、
- 翻訳や要約、画像生成など、単発で完結するタスク
- 明確でシンプルな指示を出したいとき
◆マルチターン(Multi-turn)
こちらは、複数回のやり取りを通じて会話が進んでいくスタイルです。AIは、これまでの会話の流れ(文脈)を覚えていて、それを踏まえて返答してくれます。
そのため、ユーザーの意図が途中で変わっても、柔軟に対応できるのが特徴です。
例を挙げると、
ユーザー:「猫の写真を描いて」
AI:「どんな種類の猫がいいですか?」
ユーザー:「黒猫で、夜の背景にして」
AI:「こちらが黒猫と夜の背景のイラストです。」
こんな場面に向いています。
- 会話型アシスタントとして使いたいとき
- 企画やコード開発、学習支援など、少し複雑なタスク
- 継続的なやり取りが必要なケース
ちなみに、私はセミナーや ワークショップ では、できるだけマルチターンでの会話をおすすめしています。 これは、複数回のやり取りを重ねることで、AIの力をより引き出せるからですし、価値を感じやすいという点にあります。
ただし、マルチターンにはちょっとした落とし穴がありまして…
実は、会話が長くなると「ハルシネーション(事実と異なる内容をAIが生成してしまう現象)」が起きやすくなる傾向があります(^^;
なぜマルチターンでハルシネーションが増えるのか?
1.文脈の蓄積による誤解
マルチターンでは、AIが過去の発言を文脈として保持します。
しかし、ユーザーの意図や前提を誤って解釈したまま会話が進むと、その誤解が連鎖的に影響し、誤った情報を生成する可能性が高まります。
2.曖昧な指示や省略表現
人間同士の会話では、前の文脈を前提にして省略や曖昧な表現を使います。
AIはそれを正確に補完できないことがあり、推測に頼ってしまうことでハルシネーションが発生します。
3.長い文脈の処理限界
モデルには「トークン制限(文脈の長さの上限)」があります。
長い会話では、古い文脈が切り捨てられる、重要な情報が抜け落ちることで誤った応答が生まれることがあります。
4.ユーザーの誤情報をそのまま信じる
マルチターンでは、ユーザーの発言を「事実」として扱う傾向があります。
そのため、ユーザーが誤った情報を言った場合、それを前提にしてさらに誤った内容を生成することがあります。
そのため、マルチターンの会話で、ハルシネーションを減らす場合には、以下のような工夫が大事になってきます。
- 指示はできるだけ明確に、一貫性を持たせる。曖昧な表現は避ける。
- 要点がズレていないか、途中で確認する。
- 会話が長くなったら、一度まとめて、そこからまた話を進める。
- 結果は、ちゃんと情報源を確認する(ファクトチェック)。
一方で、シングルターンでうまく結果を出そうとすると、「プロンプトエンジニアリング」的な知識がちょっと必要になってきますが、生成AIを日常的に使う中で、少しずつ覚えていけば大丈夫だと考えています。
ちなみに私は、まずは「AIと会話する機会・時間・回数」を優先して、プロンプトエンジニアリングの勉強は後回しにしていました(^^
補足・注意点
1.ハルシネーションの原因について
マルチターンでハルシネーションが起きやすいのは、文脈が長くなることでAIが過去の情報を誤って解釈することや、矛盾を避けるために「それっぽい」情報を生成してしまうことがあるためです。
ただし、これは「マルチターンだから必ず起きる」というより、「文脈が複雑になるほどリスクが高まる」からです。
2.プロンプトエンジニアリングの必要性
シングルターンで高品質な出力を得るには、プロンプト設計の工夫が求められますが、最近の生成AIはプロンプトに対する柔軟性も高くなってきており、必ずしも高度な知識が必要というわけではありません。
とはいえ、「良い問いを立てる力」は、AI活用において今後ますます重要になるのは間違いありません。
#まとめ
先ずは、生成系AIを触っていただく隙間を日常業務で、少しずつでも、生成系AIを利用する時間を日々増やしていただき、生成系AIの良さやテクニックを覚えて頂ければと考えています(^^
※ 本投稿は、弊社で運営していますソフクリ365倶楽部のTeams投稿等で案内した内容を再編したものになります。ソフクリ365倶楽部のプレミアム会員様については、倶楽部への投稿や技術情報の投稿等を閲覧、アクションすることが可能です。