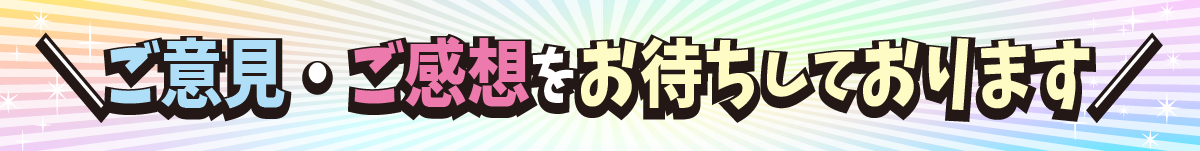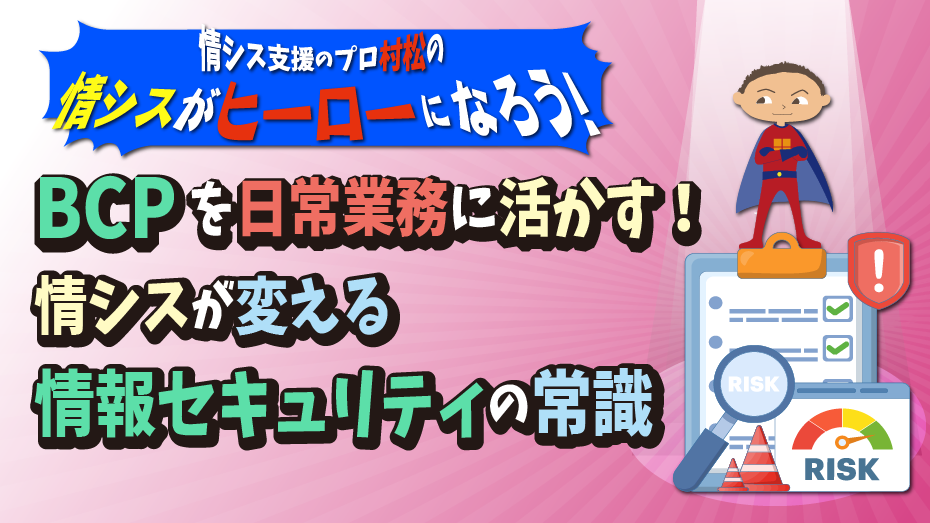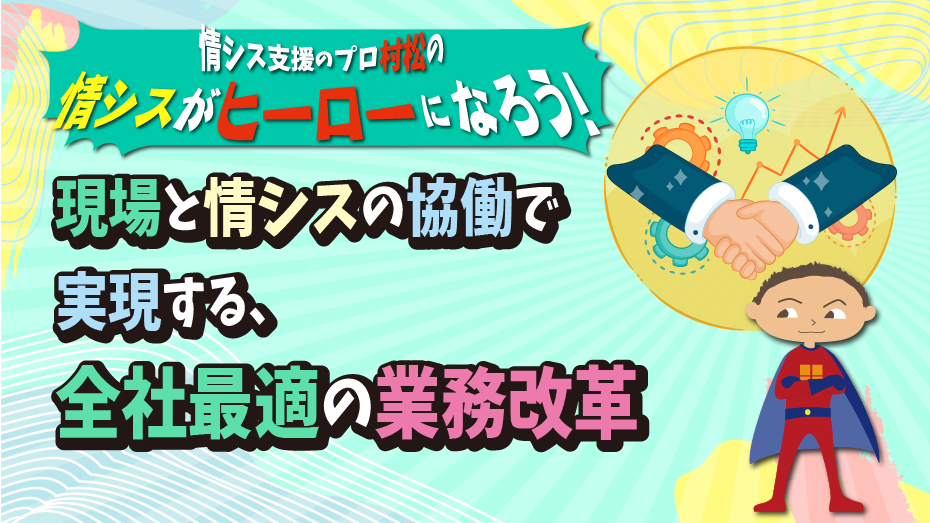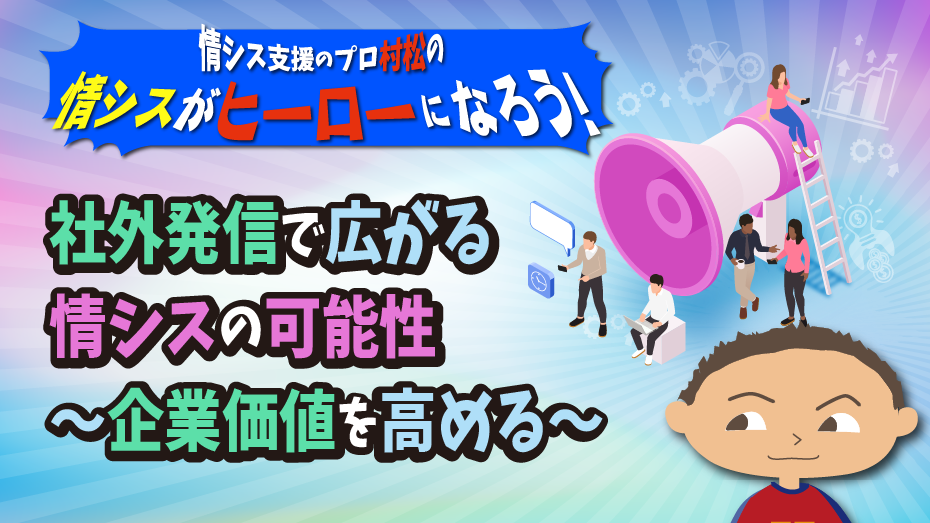
いよいよ本コラムシリーズも最終回となりました。
ここまで、組織にとって情シス活動がより価値を高めるための道筋をたどってきました。最後はその価値を社外に発信することの意義と、発信方法に焦点をあてました。
1.情シスの取り組みは“発信する価値“がある
情報システム部門、いわゆる“情シス”は、組織のインフラを支え、業務のデジタル化を推進し、部門を横断した調整を担うなど、多様な役割を果たしています。
日々の運用保守から始まり、クラウド移行、業務改善ツールの導入、セキュリティ対策、情報管理の標準化、さらにはAIの業務活用支援まで――多くの企業で、情シスは“縁の下の力持ち”として極めて広範な貢献をしています。
しかし、その活動が社外に知られることは、あまり多くありません。
それは、情シスの仕事が「社内向け」かつ「目立たない」形で行われることが多いからです。
とはいえ、だからこそ、その取り組みは“発信”する価値があるのです。
なぜなら、情シスの成果は企業の実力を示すバロメーターになり得るからです。
例えば、下記のような取り組みは、他社にとって学びになるだけでなく、自社にとっても「技術力・運用力・組織力」を示す絶好の材料になります。
- DXの具体的な事例として、自社の業務改善をどのように進めたか
- セキュリティや情報管理の実践例として、どのような考え方で仕組みを構築したか
- 社内連携・巻き込みの工夫として、どのように部署横断で変化を生み出したか
さらに、発信には次のような副次的な効果もあります。
- 自社のプレゼンス向上:
業界誌、セミナー、Web記事での露出が企業ブランドを高めます。 - 採用活動への好影響:
自社の技術力や取り組みを外に示すことが、エンジニアやIT人材の関心を引き、応募動機につながります。 - 社内での認知向上:
社外に出すという緊張感と意義が、社内でも情シスの活動を“誇れる成果”として再認識させる効果を生みます。
つまり、社外発信は「情シスが主役になる」ための手段ではありません。
むしろ、「組織としての価値を他者に伝える」ための戦略的なコミュニケーションなのです。
2.とはいえ情シスは“広報部”ではない
社外への発信が有効であるとはいえ、情報システム部門は本来、対外的なコミュニケーションのプロフェッショナルではありません。会社のブランディングやメディア対応、情報開示の戦略を担うのは、一般的に広報部門の役割です。
つまり、情シスがいきなり単独で記事を発信したり、セミナー登壇を決めたりするのは、会社の方針やリスクマネジメントの観点から見ても慎重であるべきです。
この章では、情シスの立場を整理した上で、「どこまでが独自の裁量でできて、どこからは広報などと連携すべきか」という現実的な線引きについて考えてみます。
①情シスは“発信素材の提供者”である
まず押さえておきたいのは、情シスは「発信の企画者・演出者」ではなく、「発信の中身を持つ人」だということです。
例えば、以下のような素材は情シスが一番詳しく、また、現場で実践してきたリアルな知見を語ることができます。
- 業務改善の背景や工夫した点
- 社内の巻き込み方や失敗事例
- 選定したツールや設計上のこだわり
- セキュリティやガバナンス上の工夫
これらは、広報担当者にとっては喉から手が出るような“発信素材”です。しかし、技術的な内容や運用上の細かい部分は、広報部だけでは把握できません。
だからこそ、情シスが素材を整理し、社内で共有・報告するところから“発信活動”が始まるのです。
②社外発信は「共同作業」としてとらえる
実際に社外向けに何かを出す場合は、次のような形で他部署との連携が必要です。
| 発信フェーズ | 主な役割者 | 情シスの関わり方 |
|---|---|---|
| 発信企画 | 広報・経営企画 | 素材提供・構成相談 |
| 内容チェック | 広報・法務 | 技術内容のレビュー |
| 公開・展開 | 広報 | 登壇・記事協力など |
このように、情シスは「中身の担い手」として協力するスタンスが適切です。
実際、技術系メディアでも「中の人に話を聞かせてほしい」「導入の裏話を聞きたい」というニーズは非常に高く、広報がフロントに立ちつつ、情シスがコンテンツで貢献するという構図はとても自然です。
また、いきなり社外向けに発信することに抵抗がある場合は、本コラムシリーズの
第4回
でお話したように、社内に向けた「取り組みの共有」から始めるのも有効です。
3.誰に、何を、どのように
社外への発信といっても、「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかによって、その効果も伝え方も大きく変わります。
①「誰に」発信するのか――3つの代表的なターゲット
発信先によってアプローチ方法やメッセージが変わります。情シスが主に想定すべき対象は以下の3つです。
| 発信対象 | 目的 | 想定メディア・機会 |
|---|---|---|
| 社外のIT人材(採用候補者) | 採用広報・ブランディング | 技術イベント、ブログ、メディア取材 |
| 顧客・パートナー企業 | 信頼性・技術力のアピール | 自社HPの事例紹介、セミナー登壇 |
| 社内他部署・経営層 | 活動理解と協働促進 | 社内報、イントラ掲示、全社共有会 |
例えば「採用を強化したい」のであれば、技術的な苦労や創意工夫、働きやすさなどに触れたストーリーが有効です。一方、顧客やパートナー向けには、安定性や情報セキュリティへの配慮などを強調した方が効果的でしょう。
②「何を」伝えるのか――情シスの“強み”を活かすテーマ選び
発信内容の軸は、やはり「実践知」にあります。中でも、情シスならではの観点をもつ以下のようなトピックは、外部からの関心も高く、会社の信頼性向上にもつながります。
- 自社独自のIT活用の工夫(例:ローコードツールの社内展開)
- セキュリティ強化の裏側(例:ゼロトラスト導入と社内教育)
- 組織を横断したプロジェクト推進のノウハウ
- 現場との協働や社内浸透における工夫・失敗と学び
- DX推進を支えるインフラ刷新や運用の安定化
重要なのは「誇張しないこと」です。等身大で、実体験に根ざした発信は共感を呼びやすく、他社にとっても「自分ごと」として参考になります。
③「どのように」発信するのか――形式と手段の選択
発信にはさまざまな方法がありますが、情シス部門が現実的に取り組みやすいのは以下の手段です。
| 発信形式 | 特徴 | 難易度 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 自社ブログ・note | 自由度が高く更新しやすい | ★★ | ◎ |
| ITメディアへの寄稿 | 信頼性・拡散力が高い | ★★★ | ○ |
| セミナー登壇 | 登壇者の経験が問われる | ★★★★ | ○ |
| 社内報・ポータル | 発信の練習として最適 | ★ | ◎ |
| SNS(LinkedInなど) | 個人色が出やすい | ★★ | △(慎重に) |
情シスが初めて発信を行う場合は、まずは「社内報 → 社内共有会 → 自社ブログ → 外部メディア」のようにステップアップしていくのが現実的です。
また、発信内容にあわせて、図解やビフォー・アフターの定量的なデータを入れることで、伝わりやすさが一段と高まります。
4.情シスの発信ポリシーを考える
情シスが社外発信に取り組む意義や手法について見てきましたが、同時に注意すべき点もあります。それは、「発信が目的化してしまうリスク」や、「情シスの本業とのバランス」です。
発信を企業価値向上の手段として活かすためには、情シスとしての“発信ポリシー”をあらかじめ定めておくことが大切です。
①発信ポリシーの必要性
多くの情シス部門では、限られた人員で日々の運用やプロジェクト対応に追われており、発信に割けるリソースは潤沢ではありません。その中で発信を行うには、「どこまでやるのか」「何を目的にするのか」を明確にしなければ、かえって現場に負担を強いることにもなりかねません。
発信ポリシーは、そのガイドラインとなるもので、次のような効果があります。
- 社内での発信活動への理解・協力を得やすくなる
- 発信の選定や優先順位の判断基準が明確になる
- 広報部との役割分担や連携がしやすくなる
- 情報漏洩や誤解を防ぎ、リスクを最小限にできる
②発信ポリシーの5つの柱
以下に情シスの発信ポリシーとして一般的に検討した方がよい5つの項目を紹介します。
| ポリシー項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的の明確化 | 発信の主な目的は「採用支援」「ブランディング」「社内連携強化」など。軸をぶらさずに継続する。 |
| テーマの選定基準 | 実体験に基づいた“再現性”ある取り組み、他社にとっても価値のある知見に限定。自己宣伝に終始しない。 |
| 関係部署との連携 | 発信内容に関わる部署(広報・人事・法務・経営層)と連携・合意形成を行う。広報とは必ず相談を。 |
| リスク管理 | 発信内容の情報分類を明確にし、守秘義務や機密情報の扱いに配慮。外部発信前のレビュー体制を整備。 |
| リソース配分 | 発信は本業に支障をきたさない範囲で。年数回の投稿・登壇にとどめるなど、現実的な頻度設定を。 |
③広報部門との役割分担
情シスが社外発信をする際、広報部門は避けて通れない重要なパートナーです。
例えば:
- プレスリリースや外部メディア対応は広報が主管
- 技術的・業務的な背景説明は情シスが原稿協力
- ブログやSNSのトーン&マナー、ブランドガイドラインは広報が管理
このように、発信における「表現」「戦略」「統制」の側面は広報が担い、情シスは「中身」や「現場の声」を提供する、という分担が理想的です。
協力関係を築いておくことで、情シスの発信はより洗練され、安全かつ効果的に実現できます。
5.まとめ:情シスの新しい未来を描く
全10回にわたってお届けしてきた「情シス応援コラム」は、情シス(情報システム部門)が“裏方”の存在にとどまらず、組織の中核として価値を発揮していくための視点と実践をテーマに進めてきました。
このコラムの出発点は、「情シスはもっと誇っていい仕事をしている」という想いでした。日々のシステム運用やトラブル対応に追われがちな情シスですが、その実態は、会社の仕組みと業務を根本から支える、非常に高い専門性と責任を伴う仕事です。
このコラムを通して伝えたかったことは、情シスが「何をやるか」だけでなく、「なぜやるのか」を明確にすることで、部門の立ち位置が大きく変わるということです。
- 単なるトラブル対応 → “業務全体の質”を守る守り神へ
- システム導入の実務担当 → “業務改善のファシリテーター”へ
- 社内で完結する縁の下の存在 → “社外ともつながる価値発信者”へ
このような進化は、一足飛びにはいきませんが、日々の業務の中で少しずつ意識を変えていくことで、確実に実現できます。
社会や技術の変化が激しい時代において、情シスの仕事はますます複雑で難しくなっています。しかし、それと同時に、組織を変革し、新しい価値をつくる「主役」になれるポジションでもあります。
このコラムをきっかけに、一人でも多くの情シスの方が「今までのやり方を少し変えてみよう」と思っていただけたなら、それが本シリーズの最大の成果です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
本シリーズは今回で終了となりますが、次回シリーズでは”生成AI時代における「マスターナレッジxデータマネジメント」”と題した内容を企画しています。
生成AIに関する最新情報、活用情報はあふれていますが、組織として生成AIを活用するには、元となるデータや情報管理がカギになるという点があまり知られていないように感じます。
そこで、より身近なストーリーを通してデータ管理/ナレッジ管理について学んでもらおうという意欲企画です。是非次回シリーズもご期待ください。
情シスの未来は、あなたの一歩から始まります。これからも、“応援しています”。
おわりに ~ご意見お聞かせください~
本コラムの主旨は単に情報やノウハウを伝えることではなく、読者の方からのフィードバックを受けて各テーマの解像度を高め、実践を積み上げていきたいというものです。
皆様の組織ではどのような課題を持っていますか、解決した事例はありますか。コラムの中で是非ご意見を紹介させてください。
▼是非こちらのフォームよりご意見、ご感想をお寄せください。▼
■著者紹介■
村松 真(むらまつ まこと)
出身:東京都稲城市
ひとこと:情シスの皆様に寄り添うコラムをお届けします
Microsoft Top Partner Engineer Award 2023年 受賞
エンジニアとしてのキャリアに加え、経営や組織開発、文書管理、Microsoft の製品知識、情報セキュリティなど幅広い視点で、中堅中小企業のお客様を支援。

大学に入学した1982年からコンピューターにさわりはじめ、社会人になってからはプログラマー、SE、開発管理などソフトウェア開発全般を経験しました。その後日本マイクロソフト社の有償サポートのマネージャを経てソフトクリエイト社に入社しました。
ソフトクリエイト入社後はサーバー構築やクライアントのドメイン移行や運用支援など、インフラ構築系案件のプロジェクトマネージャーとして経験を積んできました。
2019年に中小企業診断士の資格を取得し、コンピューターシステムだけではなく、経営視点や組織開発、文書管理、情報セキュリティなど様々な角度からお客様のソリューション支援を行っています。
長年情シスのお客様と接していて、頑張っているのになかなか報われない姿をみてどうやったら応援できるだろうかと考え続けてきました。
DXによる変革と、AI活用による業務変革がすべてのお客様に求められる現代において、情シスの価値が爆上がりするチャンスが到来しました。
この機を捉えてブレイクする情シスに寄り添うコラムをお届けしたいと思います。