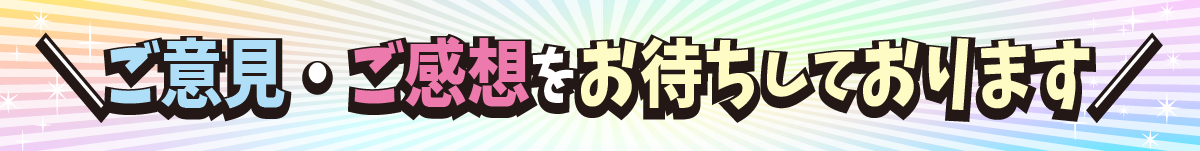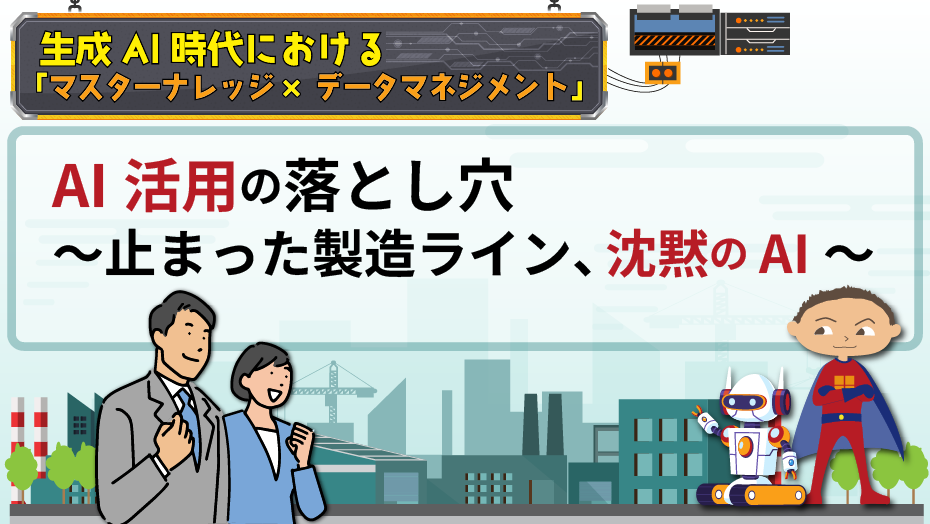
本コラムに関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
今、システムの世界はもちろんあらゆる業界に生成AIが入り込み始めています。
しかし生成AIで業務改善した事例は聞くものの、「業績がxx倍になりました」といった話はまだあまり耳にしません。それはなぜでしょうか。
インターネットのオープンな情報を基に学習したパブリックAIを活用するだけでは、個人の業務改善はできても、組織としての業務プロセスの改善にはなかなかつながらないからです。
この課題の本質に迫るには、AIを使う側――つまり私たち自身の持つ「知識」と「データ」がどのように管理されているのかを見直す必要があります。
現場の知恵やノウハウは、果たして誰もが使える形で整理・共有されているでしょうか?
AIの活用を本当に組織の力に変えるためには、データマネジメントやナレッジマネジメントのあり方を問い直すことが不可欠です。
本コラムでは、シリーズを通して「マスターナレッジ×データマネジメント」の課題を、現場で実際に起こりがちなエピソードをもとに考えていきます。
毎回、架空の会社「株式会社トリリス精機(略称:トリリス)」の現場を舞台に、生成AI時代における知恵とデータの活かし方について、物語形式で掘り下げていきます。
まずは第1回のエピソードをご覧いただき、データと知識の管理の重要性について、皆さんと一緒に考えていければと思います。
AI活用の落とし穴~止まった製造ライン、沈黙のAI~
老舗B2B機械メーカー「株式会社トリリス精機」。
創業から半世紀、町工場の匂いと最新鋭のロボットが同居するこの会社で、情報システム部は「DXで現場を軽くする」を合言葉に、紙の申請を電子化し、点検記録をタブレットに置き換え、少しずつ“面倒くささ”を削ってきた。
相馬直哉(35)は、その実務担当だ。
朝は工場棟のWi-Fi点検、昼は発注システムの小改善、夜は社内チャットボットのチューニング。忙しいが、仕事は嫌いじゃない。
その日の午後、ラインから緊急通話が飛び込んだ。
「ライン3が止まりました。 センサーが反応しません!」
相馬は走った。保全担当の視線が集まる。
停止箇所は見覚えのあるユニットだった。――ひと月前に改修したところだ。
「直哉さん、改修の内容と手順、どこにあります?」
胸がざわつく。設計書は、たしか共有フォルダの『Fin_2024』配下に……いや、プロジェクトの個人フォルダに移したか。
検索窓にキーワードを入れる。ヒットはする。似た名前のPDFが四つ。更新日はバラバラ。どれが最新だ?
「担当の斎藤さんは?」
「出張移動中。電波が弱くて繋がりません。」
――嫌な汗が背中をつたう。
相馬は最後の望みをかけて、最近導入したAIチャットを開いた。
<先月のライン3改修、変更点を教えて>
画面が数秒沈黙し、無難な説明を返してきた。
「センサーの一般的な故障要因は……」「まずは配線とドライバを……」
当たり障りのない答え。 役に立たない。
社内の資料を食べさせていないAIに、社内の真相は語れない。
時間だけが流れ、ラインの周りの熱と焦りが濃くなる。
相馬はかすかな記憶をたどった。――改修後、取引先に報告メールを送った。そのスレッドに、何か添付しなかったか?
受信箱をさかのぼる。外部とのやり取りフォルダ、さらにその奥。
あった。『改修報告(先方確認済)』。
添付ファイルを開くと、必要最低限の仕様書のほかに、見覚えのないスライドが混じっている。
(え、これ……社内用のメモだ。)
センサー感度の初期値、しきい値の微調整、現場での“コツ”が箇条書きになっている。
どうやら斎藤が、別の資料といっしょに誤って送ってしまったらしい。外部に出す必要のない情報なのに。
「相馬さん、これでいける?」
保全担当が工具を手に問う。相馬はうなずいた。
スライド通りに設定を戻し、センサーの角度をほんの少しだけ調整する。
――機械が、低く息を吹き返すように動き出した。周囲から安堵の声が上がる。
復旧はできた。だが胸の奥に、別の重さが残った。
(たまたま見つかった、たまたま送られていた、“たまたま”の綱渡りで動いている。)
夕方、本社の役員会議室。緊急の集まりだ。
社長、工場長、各部門の長、そして情報システム部のマネージャー三浦智子(42)が座っている。
相馬は一連の経緯を、できるだけ淡々と話した。誤送信された社内メモが復旧の決め手になったことまで。
短い沈黙のあと、社長が口を開く。
「偶然に助けられる運用は、運用とは言わない。 今日、会社は止まりかけた。
DXだ、AIだと言う前に、我々の“知恵”がどこにあり、誰が守り、どう見つけるのか
――それを決めねばならん。」
視線が三浦に向く。彼女は静かにうなずいた。
「社長、社内データ改善プロジェクトを立ち上げます。
責任者は私。実務は相馬を中心に。
最初にやるのは難しいITではありません。
置き場所を一つに決め、名前をそろえ、最新版を明らかにする。
そして、見ていい人だけが見られるようにする。そこから始めます。」
「いつまでに?」
と工場長。
「まずは二週間で計画と最初のルールを。次の二週間で、よく使う文書から“本棚”を作ります。」
社長は短く考え、にっこりもしないで言った。
「やってくれ。 必要な協力は出す。今日のような運は、二度と使わない。」
会議が解散になり、誰もいなくなった廊下を歩く。
窓の外は、暮れかけた空に工場の煙突が影を落としている。
「直哉くん。」
背後から三浦が呼んだ。
振り返ると、彼女は疲れた目で、それでも少し笑っていた。
「AIは鏡だね。映ったのは、わたしたちの散らかった棚。
棚を作ろう。 ちゃんと“置いて”、ちゃんと“探せる”ように。」
相馬は深く息を吸った。
たまたまの幸運に頼らない、ちゃんとした仕事を、いまから始める。
胸の内で、ひとつだけ言葉を結ぶ。
――知恵の本棚を作る。ここから、やり直す。
さて、皆さんどのように感じましたか?
うちは業種が違うから、うちはもっとしっかりしている、いろいろ違いはあるでしょうが、データマネジメントやナレッジマネジメントに課題を持たない会社はほとんどありません。
データマネジメント/ナレッジマネジメントと一口にいっても、様々な切り口があり、ガバナンスやセキュリティやデータ品質などきりがありません。
そこで、本コラムではDMBOK2というデータマネジメント知識体系を参考に、ナレッジマネジメントの要素を加えて毎回一つのテーマについて解説していくことで、データマネジメント/ナレッジマネジメントレベルの向上をめざしてまいります。

出展:「データマネジメント知識体系ガイド 第二版」より抜粋
“株式会社トリリス精機の相馬さん”とともに、“知恵の本棚”作りの旅に出ませんか?
本コラム第2回「迷子ゼロの三原則――場所・責任・正本(+分類)」では、情報管理の土台となる基本ルールを体系的に整理します。
本コラムの主旨は単に情報やノウハウを伝えることではなく、読者の方からのフィードバックを受けて各テーマの解像度を高め、実践を積み上げていきたいというものです。
皆様の組織ではどのような課題を持っていますか、解決した事例はありますか。コラムの中で是非ご意見を紹介させてください。
▼是非こちらのフォームよりご意見、ご感想をお寄せください。▼
■著者紹介■
村松 真(むらまつ まこと)
出身:東京都稲城市
ひとこと:情シスの皆様に寄り添うコラムをお届けします
Microsoft Top Partner Engineer Award 2023年 受賞
エンジニアとしてのキャリアに加え、経営や組織開発、文書管理、Microsoft の製品知識、情報セキュリティなど幅広い視点で、中堅中小企業のお客様を支援。

大学に入学した1982年からコンピューターにさわりはじめ、社会人になってからはプログラマー、SE、開発管理などソフトウェア開発全般を経験しました。その後日本マイクロソフト社の有償サポートのマネージャを経てソフトクリエイト社に入社しました。
ソフトクリエイト入社後はサーバー構築やクライアントのドメイン移行や運用支援など、インフラ構築系案件のプロジェクトマネージャーとして経験を積んできました。
2019年に中小企業診断士の資格を取得し、コンピューターシステムだけではなく、経営視点や組織開発、文書管理、情報セキュリティなど様々な角度からお客様のソリューション支援を行っています。
長年情シスのお客様と接していて、頑張っているのになかなか報われない姿をみてどうやったら応援できるだろうかと考え続けてきました。
DXによる変革と、AI活用による業務変革がすべてのお客様に求められる現代において、情シスの価値が爆上がりするチャンスが到来しました。
この機を捉えてブレイクする情シスに寄り添うコラムをお届けしたいと思います。